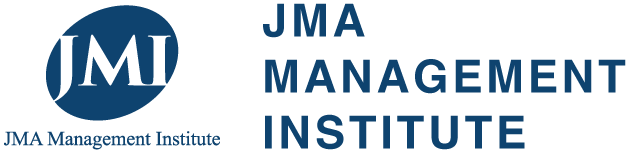経営者として活躍するOB
EBLアドバンストマネジメントコースに参加して(2022年9月20日)

2015年度EBLアドバンストマネジメントコース修了
山口 賢二 氏メタウォーター株式会社 代表取締役社長
1.日本能率協会「JMAマネジメント・インスティチュート」(JMI)ご参加のご感想・思い出などをお聞かせください。
(参加を通じて役に立ったと感じたこと、社長の仕事で活かされている等)
他流試合の場に参加し、経営について大いに語り合う
2015年の執行役員就任時、人事部門からの勧めでJMI「EBLアドバンストマネジメントコース」に参加しました。事前課題が多く大変でしたが、異業種のメンバーと企業経営や事業運営について気兼ねなく話し合えたことが良かったです。また、講師も考え方や理論の押し付けをせず、正解はない問いを参加者に考えさせるスタイルで、自分にとってしっくりきていて、とても有意義でした。
企業のミッションやリーダーとしてのパッションの大切さ
何よりも、企業の存在意義・目的を明らかにすることや、パッションをもって組織を動かすことの大切さなど、経営者としての“気持ちの持ち方”について学ぶ機会となり、のちに(2021年に)社長に就任して、それらの考えが非常に役立っています。
現在は「パーパス経営」が大事と言われる時代ですが、声高に言われる以前からその大切さをコースの中で学ぶことができました。退屈な研修も世の中にはあるが、このコースは時間がもったいないと感じることが全くありませんでした。
2.社長としてどのような組織づくり・人づくりをお考えですか。
部下・メンバーの個性や強みを最大限引き出すマネジャー育成
よくあることですが、役職が上がると、それが自分の能力だと勘違いする管理者・幹部がいます。「自分は優秀で部下は未熟」だと思ってしまうのですが、それは良くないです。ポテンシャルの高い部下は多いし、世の中自分よりも優秀な人間はたくさんいます。大事なのは、部下の個性や強みを良く見て、その強みを引き出してあげること。育てるのではなく、育つことを支援するのが上司の役割でしょう。そういった謙虚な気持ちで部下と接してほしいです。上から抑えつけるようなマネジメントでは、部下は自分の器以上には成長しません。
自分の役割範囲を越境し、“自責で課題解決に挑む”人材・風土づくり
それから、自分ののりしろを多く持ち、活用してほしいです。のりしろとは、自分の役割範囲を超えて活躍すること。組織が大きくなると、いわゆる「ポテンヒット」のような事態が起こります。複数の機能・部門の丁度間に位置する問題を、双方が他責にして拾いに行かない、という状況です。当社にも大企業的な風土、即ち、部門間の壁がどうしても存在します。それを取り除き、互いに相手のことを気遣い、“お互いさま”で助け合う関係をつくる。誰かがミスをしてもカバーしあう体制。そういった企業風土が私の理想です。そのためには、人に関心を持ち、他部門に関心を持ち、人のせいにしない、自責で問題を発見・解決する姿勢が不可欠です。これを当社の強み(差別化ポイント)にしていきたいと思い、取り組んでいます。まさにこれが当社の“人的資本経営”の根幹です。
“損して得取れ精神”の体現
また、私の信条として、“損して得取れ精神”があります。先にこちらから相手にとって良いと思うことをしてあげる。その姿勢が、その後の良い関係、良いビジネスを創っていると信じています。私は日頃からこの考えを社員に伝えています。また、海外M&Aを行う際にも、この日本的な考えを理解してもらえる素地のある会社を選ぶようにしています。海外企業には理解が難しいと思うでしょうが、理解のある企業も存在ます。これは当社の海外事業展開の重要な視点の一つであり、当社にとって“素性のいい会社”選びのポイントともいえます。
これからのリーダーに必要な力とは
部下に仕事を任せ、上司は黙って耐えること、あれこれ口を出したくなるでしょうが、上に立てば忍耐力が必要。“放任”でも“手取り足取り”でもダメ。どうやったらうまくいくか、しっかり部下に考えさせ、気づかせること。そのために、部下をしっかり観察し「人材の見極め力」を養うことが上に立つ人には求められます。
また、知識でものをいうのではなく、「知識+経験=知恵」が必要でしょう。知識だけでは人は動きません。経験・思い(情熱)を入れて働きかけ、部下に達成感を感じさせます。
以上、整理すると、「忍耐力」「考えさせる・気づかせる力」「達成感」「情熱」「見極め力」が大切だと思っています。
3.最後に、今後取り組むべき重要な経営課題や自社の方向性について、お考えをお聞かせください。
「世のため・人のため」の役目、日本の資産を後世に残す
当社は、水・環境インフラの課題解決に取り組んでいます。上水道・下水道は、私たちの生活にとって無くてはならないインフラですが、日本は今人口減少に向かっており、水インフラの維持のためのヒト・モノ・カネの経営資源がすべて不足しつつあります。地方自治体では、従事する担当者の人員減、また、人口減少に伴う財源の縮小(財政難)により、インフラ維持が危機に直面しています。この状態を改善するため、私たちのような民間の力で、住民が安心して暮らせる社会の構築が必要です。その役目を、当社はしっかりと担っていかねばなりません。
この重要な社会課題の解決に資する人材を育て、事業を広げていくことが重要な課題であり、私たちの使命だと考えています。活躍範囲は日本にとどまらず、海外にどんどん広がっています。まさに「世のため人のため」の仕事。情熱をもって取り組んでいきたいです。良い日本の資産を後世に残す、そういった仕事をこれからも当社一丸となって続けていきたいと思っています。